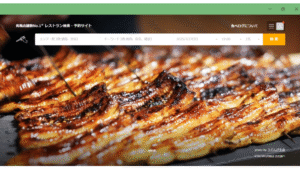2025年8月7日、茨城県沖で訓練中だった航空自衛隊のF2戦闘機が墜落した事故、まずは人命が失われる事態ではなく、胸を撫でおろした。しかしマスコミはこのF2戦闘機が1機約120億円することまでは報じても、それが高いか安いか、そもそも安全性に問題はないのか、ということまでは報じない。カウンターPRESSは元空自の人物に連絡を取り、報道に欠ける部分を補うことにした。
まず、1機120億円という値段は高いのか?
「最新型のF-16Vと同程度で、高い戦闘機と言っていいと思いますよ。調達数が約100機しかないので、(大量生産効果が得られず)1機あたりが高額になります。さらに、主翼に炭素繊維複合材を使い、国産電子機器も多数搭載しているので、それも価格を押し上げていると思います」
自動車事故のように、機体に保険は掛けられているのだろうか?
「いえ、それは無理ですよ。戦闘機のように高額で、訓練や任務で高いリスクに晒される装備品に保険をかけようとしたら保険料が高額になります。個別の資産に保険をかけるより、損失が発生した際に自分自身で補填する方がコストは安く済みますよ」
核心はここからだ。民間の航空会社が運用するエアバス機やボーイングの機体に比べ、自衛隊機は事故の確率が妙に高くはないだろうか? 例えばF2戦闘機だけでも、2007年10月には名古屋・小牧基地で離陸に失敗して墜落・炎上(パイロット2名は軽傷で脱出)、2019年2月には山口県沖での訓練中に墜落(乗員2名は脱出)、2021年4月には編隊飛行中に空中接触(軽微な損傷で帰還)、そして2025年8月に茨城県沖で訓練飛行中に墜落(パイロットは緊急脱出し無事)。最近では、2025年5月に起きたT-4 練習機の墜落事故も記憶に新しい。実際はどうなのか?

命がけとは言えないけど、でもやっぱり「命がけ」
ここで少し余談を許してほしい。筆者は以前、陸上自衛隊で不発弾の処理に携わった経験をお持ちの方に話を聞いたことがある。命がけのお仕事に感謝します」といった話をすると、彼は意外なことを言った。
「命がけじゃダメなんです(笑)。不発弾も安全に処理できるマニュアルがあって、我々はそれをもとに処理してるんですよ」
要するに自衛隊は「命がけ」を認めない、認められないのだ。そんな前提を元に筆者と元空自の方の話を聞いて頂きたい。「自衛隊機の事故、多くないですか?」と聞くと彼はこう言った。
「一般的にですが、航空機は飛行時間が長くなるほど完成度が高まります。その点、民間機は有利なんですよ。例えばエアバスのA320とその派生機は世界中の航空会社に1万4千機以上が引き渡されていて、何十年も飛んでいます。その分、改良されているから事故は少なくなります。一方、F2は100機程度しかつくられておらず、民間機に比べ累計総飛行時間(F2全機の飛行時間の合計)が圧倒的に少ない。しかも急上昇・急降下、失速回復など機体に負担がかかる訓練も行いますので……」
民間機より事故が多いのは仕方ない、と?
「いえ、口が裂けてもそんなことは言えません。私が言えるのは、般論として、累計総飛行時間が長い機種は安全性も高い傾向がある、ということまでです。
……あとはお察しください」
ようするに、航空自衛隊は絶対に言えないが、戦闘機は民間機に比べ累計総飛行時間が少なく、機体に負荷がかかる訓練も行うため、現実的には不測の事態も起きやすい、というのが事実のようだ。
ちなみに筆者はそれを聞き「だから自衛隊はダメだ」とは考えない。むしろ、相対的に事故の確率が高いと思われる機体に乗って任務をこなす自衛隊のパイロットの方たちに改めて敬意を表したい。皆さんはいかがだろうか?
「事故の教訓は必ず活かされる」と信じるしかない
この話は彼に「空自魂」を思い出させてしまったようだ。彼は既に空自の人ではないにもかかわらず、空自がいかに事故の教訓を取り入れ、安全性の向上を図っているかを熱っぽく語る。
「航空自衛隊の航空機事故は『航空事故調査委員会』という組織によって徹底的に分析されます。誰が悪かったのか、という犯人捜しでなく、正確な原因を究明して再発防止策を立てるんです」
事故の分析は、主に以下のステップで進められるという。
「まずは検証に必要なものが回収されます。機体の残骸や『フライトデータレコーダー』『コックピットボイスレコーダー』などです。次にこれを解析します。フライトデータレコーダーには機体の速度、高度、エンジン出力、パイロットの操縦桿の動きなど、墜落に至るまでの詳細な飛行データが時系列で記録され、分析すると機体に何が起きていたかが客観的にわかるんです。さらにボイスレコーダーに記録されたコックピット内のパイロットの会話、管制官との交信、警報音なども解析して、パイロットが状況をどう認識し、どう対処しようとしていたかも分析します」
同時に、関係者への聞き取りも行われる。機体を整備した整備員、飛行計画に関わった隊員、交信していた管制官だけでなく、心身の状態が許せば、救助されたパイロットからも詳細に話を聞くという。
「さらには機体の調査が行われます。残骸を細かく調べ、金属疲労の痕跡、エンジン内部の損傷、火災の跡、鳥が衝突した痕跡など、物理的な異常がなかったかを確認するんです。
その上で、事故原因は人的要因なのか、機材的要因なのか、環境的要因なのかを突き止めていきます」
では、これらのデータは活かされているのか? 彼は事故の歴史と、事故を受け何が変わったかを改めて調べ、詳細に教えてくれた。
「2007年10月に名古屋・小牧基地で離陸に失敗して墜落・炎上した事故では、電気系統の配線不良によって操縦に異常が起きたとされ、配線経路・固定方法の見直し、整備時の電気系統点検が強化されています。
ほか、2011年の東日本大震災では松島基地(宮城県)に津波がきて18機が浸水し、5機は廃棄、されています。この教訓も活かされ、駐機場を高台に移す、移動可能な簡易シェルター設置する、事前退避計画を強化する、といった対策が実施されています」
様々な企業で「PDCAサイクルを回す」ことが勧められる。Plan (計画)、Do (実行)、Check (評価)、Action (改善) 、この4つを繰り返すことで、業務の効率化や生産性、安全性の向上がはかれる、というものだ。
筆者は飛行機もこれと同じと感じた。空自も当然、事故は防ぎたい。整備も万全を尽くしているはずだ。しかしそれでも――自衛隊はこうは言えないが「事故が起きることはある」のだ。ただし、事故が起きたら徹底的に調査し、改善プランを実施し、次の事故は確実に防ぐ、戦闘機のような飛行機の進化は、それしか方法がない。
ようするに、120億円の機体は墜落した、しかし必ずこの教訓は活かされると信じよう、というのが筆者の結論だ。同時に、「飛行機の進化」や「120億円」より大切な空自パイロットの方の生命が無事でよかった、とも感じた。